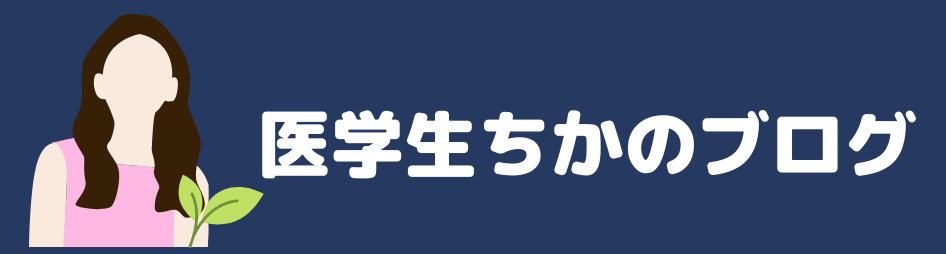こんにちは、ちかです。
今回のブログでは、大学受験(特に医学部受験)について書きます。
主に医学部の新入生、低学年の方向けの内容になっています。特に、第一志望には合格できなかった方に読んで欲しいです。
医学部に合格すること自体が狭き門
前提として「医学部に合格するだけですごい」というのが個人的な意見です。筆者はラッキーにも推薦入試で医学部に入れてしまった人なので、これは自分を棚に上げているわけではなく、一般受験で入る人は本当にすごいなとただただ感心しているだけであります。
例えば私立の一般受験の倍率は18~20倍です。それってざっくり言うと、この中から選ばれた一人ってことなんです。
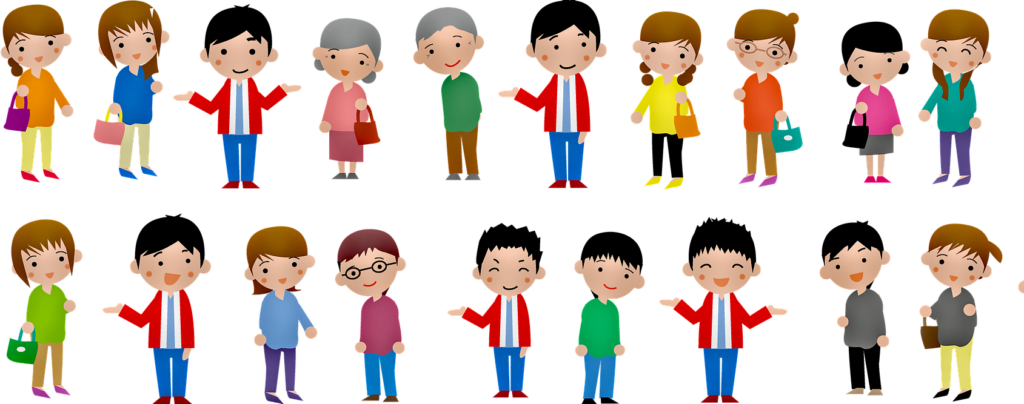
医学部に入った先は医師になることですが、やはり同じ医学部の中でも、「この大学が良い」みたいな希望ってありましたよね。「第一志望いくぞー!」みたいな感じで。
もちろん中には第一志望に行かれる方もいますし、それは本当に素晴らしいことです。しかし現実は、定員が限られている医学部受験において「100%努力が報われる」は残念ながらあり得ません。経済的な事情など、努力以外の要素も大きいので、頑張ったとしても、第一志望に受かるのは至難の業でしょう。
実際には、自分の第一志望以外の大学に通っている、という方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?
私もどちらかといえば後者なのですが、3年生の今となっては自分の入った大学が、色んな意味で第一志望だったなぁと、振り返ることができます。
そこで最近すごく思うのは、「入学すると決めた大学ならば、他に行きたい大学があったとしても、そこで精一杯楽しく過ごせたら、結局ハッピーなんじゃない?」ということです。どうせ大学生活を送るなら、楽しくて充実してる方が絶対に良いじゃないですか?!ね!
これは単に「ポジティブ人間になりなよ!」ということでは全くなく、あなたの行動&考え次第でどうにでもなるよ、というメッセージです。
ということでこの記事では、自分の入った大学を、自分の理想に近づけるには、具体的には何をしたらいいのか?、筆者の経験をもとに掘り下げていこうと思います。
サンプル数1なので、全員に当てはまるかは分かりませんが、参考になるかも、と思ったらぜひやってみてください。
この記事を読んだあなたが「大学生活楽しい!ここに来てよかった」と心から思えるようになっていただけたら、嬉しいです。
1 気の合う親友、仲間を持つ
幸福度∝人間関係の良さ
やっぱり、人間関係がどれだけ充実しているかは、幸福度に直結します。
どんなに学業的に環境が良くても、周りの人とうまくやっていけなかったり、友達がゼロとかだと辛いです。しかし逆に、環境がちょっと悪くても人間関係に満足していれば、その環境もこの人達となら一緒に乗り越えようと思えるでしょう。
気の合う親友、仲間がいれば、「この人たちと出会うために、自分は〇〇大学ではなく、この大学に受かったんだ」と思えるようになるのです。
目指すところが同じだから、仲間を見つけやすい
どうやって仲間を作るかなんですが、部活の同期や連番(出席番号が近くて実習が同じになる人たち)など、どんな繋がりでも良いので、一緒に医学部生活を乗り越える仲間を見つけてみてください。
「見つけてみてください。」と言うのは簡単ですが、実際行動に移すのは難しいですよね。(笑) よっぽどコミュ力がない限り、特にコロナ禍での新入生にはハードルが高いと思います。
しかしありがたい(?)ことに医学部には「試験に受かって無事進級」と言う共通目標があり、みんな目指す方向が同じなので、仲間は作りやすいです。
試験勉強が大変なので、「一緒に勉強しない?」とか、「あの先生のまとめノート作ってる?交換しよ!」的な感じで、繋がりを作っていくのも一つの手です。
わたしはやったことないですが、ZOOM勉強会とか開いたら、楽しそうだし仲良くなれそうですね。オンラインばかりで友達と会えないのはやっぱりサビシイ...
2 大学の強みを見つけて、活用する
これはしないともったいないです。
あなたも受験生の時、「自分のアピールポイントってなんだろう?」と探して、調査書に書いてもらったり、願書に書いたりしたと思います。
人間一人ひとりに個性があるように、医学部にもその大学ならではのカラーがあります。
カリキュラム、進級のきつさ・ゆるさ、部活の本気度、教授との距離、卒業生とのコネクション、留学制度、面倒見の良さ、研究に力を入れているか、、、などなどいろいろ要素があります。
大学案内のパンフはあんまり当てにならない
やはり偏差値が高い大学は資金が豊富であったり、有名な教授が着任していたりと、世間へのアピールポイントが分かりやすいので、「それに比べて自分の大学はレベル高くないし、そんなにメリットないんじゃないかなぁ。。。」とか思っていらっしゃるかもしれません。
個人的経験をお話しすると、筆者の大学は口下手でして、大学に入って1、2年経ってから、「ええ、意外とやるじゃん!」みたいな感じで、大学の良いところに気付きました。(笑)
受験生の時に、大学案内のパンフレットを読むじゃないですか? 今思えば、あれを読むだけでは全然知らないことだらけでした。
外(世間)からみた大学のイメージと、内部の人間からみる大学の実態は、良くも悪くも解離してると感じます。
ですので、新入生のみなさんは、自分の大学の評判や、世間のイメージに惑わされず、自分の大学の長所を学生目線で探してみてください。
どうやって見つけるねん?強みって。
一番良いのは、先輩や教授など、人に聞くことです。
例えば筆者は留学したい派でして、志望校を決める時、留学制度が充実しているかどうかを気にしていました。そういう訳で、J大学や、KIF大学志望でした。(お察しください)
一方で、入学した大学はそれほど留学を推していないように見えたのですが、入学してから留学説明会に行ったり、教授に直接話を伺うと、実は他大学と比較しても制度が充実していた!なんてこともありました。
もしあなたが大学に入ってやりたいことがあれば、それについて人に聞いてリサーチしてみてください。本当に欲しい情報はネットには載っていないんです。「部活に学生生活を捧げたい!」と思うのであれば、練習がきつくても楽しい部活はどこか、情報を仕入れたり、留学に興味があるなら担当の先生に聞いてみたり、研究をやってみたければ、授業で教わった先生の研究室に質問しに行ったり、自分の殻から抜け出して少し動いてみてください。
「チキンだからそんなのムリ!」という方は誰か友達を誘ってみても良いと思います。「〇〇部の新歓行こうよ」とか、「先生のところ行こうよ」、とか。特に断る理由もないはずなので、きっとついて来てくれますよ。
ちなみに、教授の中でもその大学の卒業生(OB/OG)の場合、学生→医師→教員・教授と経験していて、大学のことを多面的に知っています。「うちの大学って、意外と□□なところ居心地良いんですよ〜。あんま知られてないですけど。(笑)」みたいな、タメになる内情が聞けると思います。
3 他大学との交流を増やす
そもそもあなたが第一志望に行くことで、得たかったものはなんでしょうか。
少なからず、「その大学で得られる人脈」があったと思います。
卒後は都内で働きたいから東京出身の知り合いを増やしたい、将来は医師としてバリバリ活躍したいから、意識の高い人たちとつながりたい、など。
しかし医学部は一学年に100人ちょっとしかいないため、あなたと同じ目標や意識を持っている人(同期、先輩後輩含め)を、簡単には見つからないこともあります。
一方全国に目を向けてみると、同期だけでも9000人いますから、自分が関わりたい人たちとの出会いのチャンスが増えます。
同じ大学ではどうしても作れない人脈は、外で作れば良いのです。
意識の高い仲間と出会う
最近はコロナのためにオンラインになっていますが、出会いを増やす方法をいくつか紹介します。
医療系の団体/サークルに所属する
地域、目的、活動内容、参加方法が異なるたくさんの団体があります。
筆者は都内の大学に通ってますが、学生団体の集まりに顔を出すことで、実際に他大学(関東地域)の同期、先輩と知り合うことができました。
首都圏の方が交流が多いイメージがありますが、現在は代わりにオンラインで行われることがほとんどなので、地域差がなく地方の学生さんにとってはラッキーです。
主な医療系の学生団体のリンクを貼っておきます↓ Facebookもチェックするといいです。
医療系の学生団体HP
・Team Medics:http://team-medics.org/
・JIMSA(日本国際医学ESS学生連盟): https://www.jimsa.org/
・IFMSA(国際医学生連盟): https://ifmsa.jp/
・AMSA(アジア医学生連絡協議会): https://amsajapan.wixsite.com/amsajapan
・KeMA(関東医学部勉強会サークル) : https://kemaeducation.wordpress.com/
関連
その他おすすめのサイト、YouTubeチャンネル
・イノシル(留学の情報がメイン):https://inoshiru.com/
・海外で働く医療者たち〜チームWADA〜YouTubeチャンネル:
https://www.youtube.com/channel/UCg_z8bKyAE2ej-oE9V01EOA
(海外で働きたい人にイチオシ。)
SNS(主にTwitter)は同志を見つけやすい
TwitterのBio(自己紹介欄)に、興味のあるキーワードを書いている人を探す方法です。医学生は「勉強垢」と称してTwitterをやっている人が結構います。
学生団体に参加するのとは違い、顔、大学名の見えない一対一の関わりになりますが、ツイートからその人の目標や行動が見えやすいです。
例えばあなたが「将来はカナダで脳神経外科医になりたい!」みたいなピンポイントな目標がある場合、「海外志向がある+脳神経外科に進みたい」ような人とつながりたいはず。Twitterはこういったニッチなつながりが作りやすいのがメリットです。
活用方法としてよく見かけるのが、アメリカの医師免許(USMLE)を取得したい学生が、Twitterで勉強仲間を見つけて、オンライン勉強会を開くパターンです。
直接会ったことのない相手とつながるのはなんだか不思議な感覚ですが、Twitter仲間でオフ会を開いている人たちもいます。(私もいつか参加したい笑。。。)
でも日本全国に医学生の友達ができたら、キャリアにプラスになるかどうかは別として、絶対楽しいですよね。
一方で、明確な目標がない場合、Twitterでのつながりはあまり生かせません。ですので、興味が広いうちは学生団体に参加してみて、まずは受け身でいろんな物を教わるのが良いかなと思います。
(最初はアカウントだけ作って見る専にしておけばOKです。)
4 教授と仲良くなる
これは【2 大学の強みを見つけて活用する】と共通するところがあります。ここで言う教授とは、広い意味で「先生」です。
教授と仲良くなることで、大学のことをもっと知ることができますし、将来のキャリアについて聞くことができます。(先生がなぜその分野に進んだのか、どういう経緯でこの大学に来たのかなど、そういう話は結構面白いです)チャンスがあれば、先生のコネクションで留学先を紹介してくれることも。。。
医学部の先生はおもに2種類
医学部の先生は、大きく基礎医学系と臨床系の先生に別れるのですが、低学年で関わるのはほとんどが基礎医学系の教授です。
基礎系の教授は学生と同じ建物の研究室にいて、臨床系の先生(医師)は病院内にいるという違いから、関わる機会が多いのも基礎系の教授になると思います。
イメージはこんな感じですかね↓ 結構雰囲気も違って、基礎の先生は学生に教えるのが好きな感じを受けます。臨床の先生はとにかく忙しいイメージ...

基礎系の教授と話してみよう
低学年の授業は、「基礎医学」と呼ばれる授業(生化学、生理学、微生物学)で、人体の正常を学びます。簡単に言えば生物、化学の延長のような内容です。
「この先生の授業面白いなぁ」と思ったら、その先生の研究室を訪問して、「ここが分かりませんでした」、「この授業の内容をもっと知りたいです」「先生はどんな研究をなさっているのですか?」など、お話しに行くと良いと思います。
研究者って、「一人で黙々と実験して...あまり人と関わらない」みたいなイメージがあるかもしれませんが、自分の研究テーマに興味を持ってくれる人には喜んで話してくれる方が多い印象です。わざわざ行くのは腰が重いかもしれませんが、意外と先生方はウェルカムだということを覚えておくといつか役立つかもしれません。
5 学内成績で上位を目指す
受験≠医学の勉強
医学部受験において、第一志望に行けなかった方の中には、内心「本当は自分はもっとできたはず。この大学は自分のレベルより低い。」などと思っている方もいるかもしれません。コンプレックスというやつですね。
しかし言ってみれば、受験の合否を左右するのは、試験で英・数・物・化・生の問題がどのくらい解けたかであり、医学部の勉強は別物です。
どの大学にも優秀な人はいる
医学部入試自体がハイレベルなため、どこの大学でもみんな基本的に優秀で、本当に頭の回転が良く、勉強熱心な人が多いです。筆者の大学は上位校ではないですが、「わぁ、すごいなぁ。マブシイ✨」という人たちが沢山います。
受験でやり残したなら、その分入ってから頑張れば良い
いわゆる学歴コンプレックスを抱えている方は、その気持ちをバネにして、医学部の勉強を人一倍頑張れば良いのです。
医学部は試験の点数がそのまま成績に表れるため、自分の頑張りが目に見えて分かりますから、上位10%に入るなどの目標を掲げるのも良いでしょう。
大学に入ってまで順位にこだわるなんて、受験生みたいでくだらないとも思えますが、
上位を目指すことで結果的に①医学の勉強に熱心になり、②将来の選択肢も広がり、ひいては③将来の患者さんを助けることにつながります。(イイコトヅクシダネ!!!)
ちなみに、ある先生がどこかで言っていましたが、「大学によってレベル(学生の平均)は違っても結局、上位層のレベルはどこも同じ」だそうです。
※個人的には、"レベル"とか、"上位"とか、人に優劣つける言葉は好きじゃないですが、端的にいうとね、って話です。気にされる方いらしたらすみません。。。
Dr.セザキングの、こちらのYouTube動画も参考にしてみてください♪
まとめ
長くなりましたが、ここまでお付き合いいただきお疲れさまでした。
結局なんだったけ!となってしまいますので、以下まとめです。
ポイント
- 出会えて良かった!と思う心友、仲間を見つける
- 大学の特長を知り、それに乗っかる(人からの情報収集が大切)
- 学内で得られない人脈は、学外で築いていく(学生団体、SNS)
- 教授と親しくなる
- 自分がいる環境で、高みを目指す
大学に対する先入観はちょっとヨコに置いて、オープンな気持ちで大学生活を送っていけば、いつの間にか楽しくなっていると思います!これからの6年間の大学生活、ぜひエンジョイしてください。
質問やご意見、相談があればお気軽にお問い合わせください!
それでは。
最後まで読んでいただきありがとうございました。